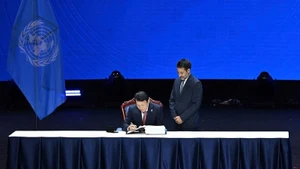2030年までに、AIがベトナムのGDPに最大800億米ドルの貢献をもたらす可能性があると予測されています。しかし、この成果を実現するためには、AI技術を習得し、発展させることができる十分な能力を持った専門家、エンジニア、データサイエンティストの人材確保が必要不可欠です。
需要に追いつかない供給
スマートシティの構築を目指し、ホーチミン市は積極的にデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、社会生活の多くの分野でAIの活用を進めています。そのため、AI人材エコシステムの育成と強化は、現状において極めて重要な役割を果たしています。
同市の強みは、国の経済の中心地であるだけでなく、AI分野を含む高度な人材を育成する多くの大学が集まっている点にもあります。
現在、同市には情報通信技術のプログラムを提供する大学が約35校ありますが、そのうちAI、データサイエンス、データエンジニアリングの分野で教育を行っているのは14校のみで、年間の新入生数は約1,000人にとどまっています。
ベトナム国家大学ホーチミン市校の科学大学による調査によりますと、企業の約60%が「現状のAI人材の質は業務ニーズを部分的にしか満たしていない」と回答し、約26%は「AI人材の育成が労働市場の要件にまだ追いついていない」としているということです。
これは、同市のAI人材が量・質ともに依然として限られており、企業の需要を満たすには不十分であることを示しています。したがって、特に新たなAI技術に対応した高度な専門スキルを持つ人材の育成・開発に注力する必要があります。
同時に、AI人材の強化を支援する国家政策も不可欠です。
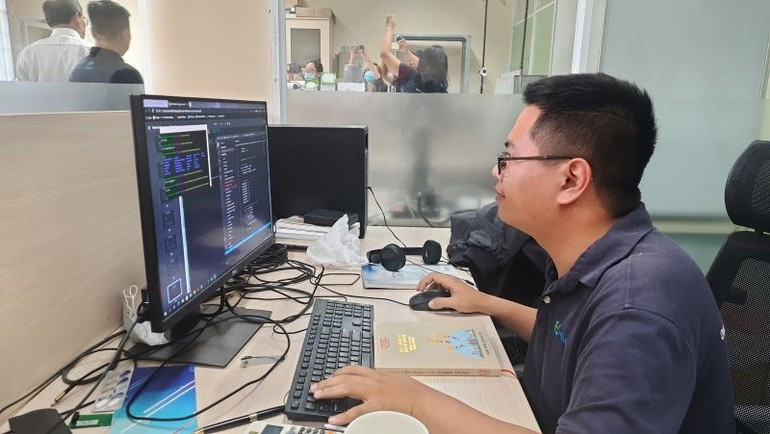
専門家たちの間では、第4次産業革命の時代において、AIがイノベーションと世界経済成長の主要な原動力となっているという考えで一致しています。
ホーチミン市にとって、持続可能な成長を目指す中でのAI人材の育成は、国際的な統合のための重要な要素であるだけでなく、競争力の強化や社会経済分野の近代化の機会ともなっています。
しかし、大きな可能性を持つ一方で、AI人材の育成には多くの課題があり、包括的かつ効果的な解決策が求められています。
CJ Vina AGRI有限会社のネットワークおよびコンピュータ管理の専門家、ファム・チ・タイン氏は、「AIは最も注目されるハイテク分野の一つとなっており、現代生活に不可欠な存在となっている」と述べました。
しかし、AIの急速な発展は人材不足という深刻な課題も浮き彫りにしています。AI人材を育成するには、AI教育・研修への体系的な投資、国際協力の強化によるグローバルな知見やリソースの共有、コミュニティや企業プロジェクトを通じた創造性と実践的応用の奨励が必要です。
さらに、学生向けのAIキャリア指導プログラムを開発し、さまざまな分野でのバランスの取れた人材育成と実践的な活用を促進するために、AI研究センターを設立する必要があります。
これらの戦略を実施することで、同市は地域および世界のAI開発拠点としての地位を確立することが期待されています。
包括的な解決策の必要性
ホーチミン市法科大学のチャン・リン・フアン氏によりますと、AI人材育成の質を高めるには、複数分野にわたる包括的かつ連携した施策が必要だといいます。
まず、教育プログラムは、ディープラーニング、生成AI、ビッグデータなど、現実の進展や世界的なAI技術のトレンドを反映して更新する必要があります。
同時に、AI倫理、社会的責任、課題解決力といった学際的スキルもカリキュラムに組み込み、学生により幅広い知識を提供すべきです。
実践的な研修モデルは、ビジネス課題を基にした実際のプロジェクトやケーススタディを開発することで拡充されるべきであり、これにより学生は理論的知識を効果的に実践へ応用できるようになります。
また、フアン氏は、大学はAI分野の教員や専門家の育成に注力すべきだと指摘した。特に、講師の再教育を優先し、最新のAI技術に関する知識を更新させることで、教育と研究のニーズにより的確に対応できるようにする必要があると述べました。

さらに、外国人研究者やAI分野の専門家をベトナムに招き、教育・研究活動に従事してもらうための魅力的なインセンティブ制度を設け、人材の質向上と国際的な知見の共有を促進すべきです。
フアン氏は、大学と企業が密接に連携することが、AI人材育成が企業のニーズに合致するために極めて重要だと考えています。この協力関係は、教育の質を向上させるとともに、労働市場の要求に適合させるための重要な解決策と位置付けられています。
これを実現するためには、企業が教育プログラムの設計に積極的に参画し、カリキュラム内容が実務の要件を反映するようにし、卒業生が採用基準を満たせるようにすることが求められます。
また、企業は大学での研究開発プロジェクトへの投資や支援を行うことで、大学の研究力を強化し、若手研究者や学生の創造性・才能を活用できるようになります。
このような密接な連携は、双方に利益をもたらすだけでなく、高度な人材の育成、イノベーションの促進、市場での競争力強化にも寄与するものです。