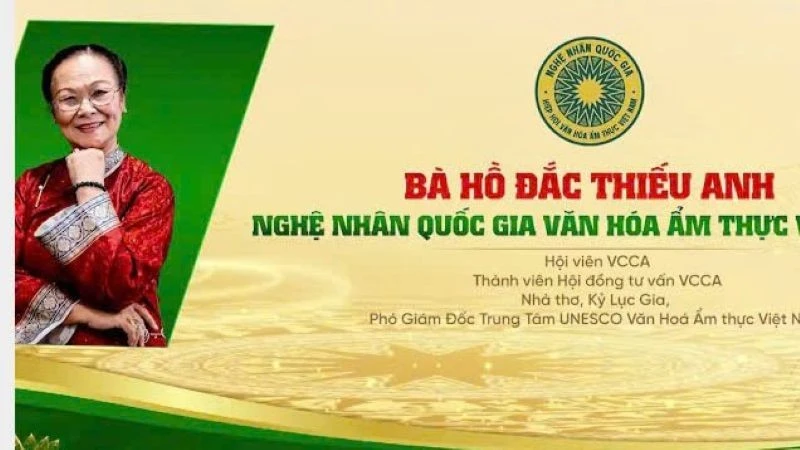マレーシアのジョージタウン世界遺産事務所のアン・ミン・チー事務局長は、世界遺産都市機構アジア太平洋地域第5回地域会議で、最大の課題は建築物の保存といった技術的側面ではなく、遺産空間の中でコミュニティを維持することにあると強調しました。
彼女は「人々が、自分たちこそがアイデンティティの所有者であり共同創造者であると感じることが重要だ」と述べました。この見解は、従来の考え方からの転換を示しています。すなわち、「保存」はもはや「博物館化」と同義ではなく、「社会的共創」と結びつくものとなっているのです。それは、遺産を人々の日常生活の一部として生かし続けるための方法であり、いま多くの都市が実現を目指している理念でもあります。
しかし、遺産が生きた空間として動的に機能するようになると、保存と開発の介入との境界は非常に繊細なものになります。祭りや歩行者天国、「文化をテーマにした」リゾートなどは、元来の価値をゆがめてしまうのではないかという懸念から、論争を引き起こすこともあります。これはかつてフエでも見られた現象です。多くの研究者は、地域社会主体の保全が語られる一方で、実際には多くの場所で地域社会が観光振興のための手段にすぎなくなっていると指摘しています。
技術的な観点から、韓国のホン・スンモ博士は、情報技術や3Dスキャン、デジタルデータを活用して遺産を復元・再現・管理する「デジタル遺産」という概念を提唱しました。その実例として、フエが将来的な王宮全体の統合的管理モデルの構築を見据え、タイホア宮殿のデジタル化を進めています。しかし、政策面から見ると、「デジタル遺産」という概念はいまだ主に技術的な枠組みにとどまっており、法的に十分明文化されているとは言えません。多くの国の文化遺産法では、無形遺産をデジタルデータでどのように管理するのか、またデジタル再現された作品の権利を誰が所有するのか、といった点がまだ明確に定義されていません。焦点となる問いは「デジタル遺産」は法的に正当な保存の形態として認められるのか、それとも単に研究を支援するための手段にすぎないのか、ということです。
さらに、デジタルによる保存には、遺産が現実の生活から切り離されてしまうというリスクも伴います。過去が「デジタル化」されると、人々はそれを「共に生きる」ものではなく、「観察する」だけの存在として捉えてしまう恐れがあります。
遺産はデータの中だけに存在するものではなく、地域社会の記憶や暮らし、文化と結びついている必要があります。
ベトナム文化遺産協会のレー・ティ・ミン・リー博士は、フエで実施された文化遺産の調査・目録化プロジェクトを知識に基づく管理の優れた取り組みとして挙げました。このプロジェクトは、800件を超える有形遺産と600件の無形遺産を網羅しています。博士は、重要なのはデータの量だけでなく、それらの情報がどのように政策の枠組みの中に統合され、活用されるかであると指摘しました。
多くの国では、文化遺産法が都市計画法、投資法、観光法などと分離して運用されています。それぞれの分野が「独自の言語」で語られるため、保全と開発が共通の基盤を見いだせない状況にあります。そのため、「遺産修復」と銘打たれた多くのプロジェクトが実際には商業事業へと変質してしまったり、逆に「保全の制約」によって伝統的な住宅地域の発展が停滞したりする事例が生じているのです。したがって、真の対立は「遺産」と「都市」のあいだにあるのではなく、「保全」という考え方そのものの中にあります。すなわち、「原形を守る閉鎖的な保全」と、「適応的な発展を認める開かれた保全」との間に存在するのです。
また、地域住民と観光客の間に生じる緊張関係も見過ごすことはできません。
これは、保全が観光経済と結びついたときに避けられない結果です。マレーシアのジョージタウン、ベトナムのホイアン、ラオスのルアンパバーンでは、生活費の高騰により住民が徐々に旧市街から離れ、古い街並みが展示空間のような存在になってしまいました。そのような状況になると、遺産はもはや「記憶の場所」ではなく、単なる「体験の背景」と化してしまいます。この逆説が示しているのは、「地域社会主体の保全」が具体的な経済的利益や明確な居住政策に結びつかなければ、理念にとどまってしまうということです。保全は生活から切り離して考えることはできず、「感傷的な理想論」だけに頼ることもできません。その実現のためには、法制度や都市ガバナンスの仕組みそのものに根本的な調整が求められます。
保存は過去だけでなく、現在と未来にも関わるものだ。人々の共存、生活の質、都市の持続可能性を確保しなければならない。多様な保存アプローチの中で、常に中心にあるのは「人」である。人こそが遺産の創造者であり、守り手であり、そしてその恩恵を受ける存在だ。しかし、人を真に中心に据えるには、その理念が仕組みや政策、法律といった形で制度化され、一貫したビジョンとして示される必要がある。なぜなら、遺産の保全とは過去に閉じ込めることではなく、未来への道を開くことだからである。
グエン・タイン・ビン フエ市人民委員会常任副委員長
フエ市人民委員会常任副委員長のグエン・タイン・ビン氏は、「保存は過去だけでなく、現在と未来にも関わるものだ。人々の共存、生活の質、都市の持続可能性を確保しなければならない。多様な保存アプローチの中で、常に中心にあるのは『人』である。人こそが遺産の創造者であり、守り手であり、そしてその恩恵を受ける存在だ。しかし、人を真に中心に据えるには、その理念が仕組みや政策、法律といった形で制度化され、一貫したビジョンとして示される必要がある。なぜなら、遺産の保全とは過去に閉じ込めることではなく、未来への道を開くことだからである」と述べました。