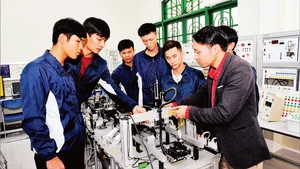国家外国語計画管理委員会のグエン・ティ・マイ・フー委員長は2017年12月22日、首相が2017年から2025年までの期間を対象とした国家教育制度における外国語教育・学習計画の調整および補足を承認したと述べました。
この承認を受け、教育訓練省(MOET)は、幼児向けの英語入門カリキュラム、初等・中等教育における10年間の英語教育のパイロットカリキュラムとすべての外国語を対象とした2018年版学習指導要領などを導入しました。その結果、外国語教育・学習活動は全国規模で統一と拡充が進んでいます。
2018年以前は、幼稚園児は英語に触れる機会がなく、小学1・2年生での外国語学習も開始されておらず、新カリキュラムで学習する小学3年生から高校3年生までの生徒の割合は36%未満でした。現在では、幼稚園児の28.5%が英語に触れる機会があり、小学校から高等学校までのほぼすべての生徒が2018年版学習指導要領に基づいて外国語を学んでいます。
多くの地域で英語以外の言語が導入されていることも注目すべき点です。上述の数字から、国が定めた教育・学習計画の実施における意識の明確な変化と努力が見て取れます。
普通教育だけにとどまらず、ほぼすべての高等教育機関(軍や警察の管轄下にある機関も含む)が、ベトナムの6段階外国語能力フレームワークに基づく外国語能力基準の適用に向けたロードマップを策定しています。
外国語で実施される先進的かつ国際連携型の教育プログラムの拡充によって、教育現場における外国語の使用が一層促進され、学生と教員の双方が語学力を高めることにつながっています。
現在、教育訓練省傘下の大学・短大における英語教師の98%が、外国語能力フレームワークのレベル5以上を取得しており、過去数年と比べると大幅な増加となっています。同時に、さまざまなクラブや課外活動、学習イベントを通じて学生間の外国語学習の取り組みが広がっており、コミュニケーション能力を磨いたり、国際的な場面でも自信を持つことができる力を育てることに寄与しています。
8年以上にわたる教育・学習計画の実施により、カリキュラム・授業内容・教授法・評価方法に至るまで、現代の国際的な教育潮流に沿って外国語教育・学習の刷新が進んでいます。これにより、学生・専門人材・労働者の外国語能力は著しく向上し、学習・研究・国際交流・労働市場への参画といった多様なニーズに応えています。
IELTS・TOEFL・TOEICなどの国際資格を有することで全国高等学校卒業試験の外国語試験が免除された受験者数は、2021年の28,620人から2024年には67,000人へと着実に増加しています。
ホーチミン市教育訓練局のグエン・バオ・クオック副局長は、現場での外国語教育・学習計画の実践経験について、同市が1998年という早い段階で学校に外国語を導入していたものの、外国語教育・学習計画の実施後にようやく、教育・学習が体系的かつ包括的になり、具体的な目標に向けて進展するようになったと述べています。
各学校では、小学1年生からの英語教育、補助的な英語学習、小学生向けの英語による数学・理科の授業など、多様な教育モデルを積極的に導入しています。さらには、日本語や韓国語など他の外国語教育の拡充も進められています。これらの取り組みは、外国語教育・学習計画の実施における各地域の適応力と主体性を示しています。
外国語教育・学習計画のもと、ハノイ教育大学では、英語による授業を行う教員の育成を目的として、数学・物理・化学・生物・情報学・小学校教育(英語)・幼児教育(英語)といった7つの教員養成課程を実施しています。毎年約250人の学生がこれらの課程を卒業し、卒業生の多くが外国語能力6段階中レベル4を達成し、それぞれの専門分野での就職を果たしています。
教員養成においては、同大学は北部の省・市と連携し、約1,000人の教員に対して外国語研修、約4,000人の教員に教育スキルに関する研修を実施してきました。このような成果は、特に2018年版学習指導要領の実施において、各地域から高く評価されています。
ハノイ教育大学は今後、3つの柱に注力する方針を示しています。英語および英語による各教科の教育・学習において、個別最適化されたデジタル学習プラットフォームと連携させながら、先端技術、特に人工知能(AI)の活用すること、外国語教員の量と質の向上と適切な待遇制度の整備を進めること、そして標準化された問題バンクの構築やとテクノロジーの活用により客観性・正確性を確保した評価方法の革新を図ることです。
同大学は、英語で授業を行う教科の教員養成の拡充、英語を第二言語とするモデル校の設立、さらには卒業時の学修成果を国際基準に合わせて標準化することを目指しています。
教育訓練省常任副大臣のファム・ゴック・トゥオン氏は、現在国際化の流れの中で、ベトナムの学生やそのほかの国民をグローバル人材として育成することが不可欠であり、国家教育制度における外国語教育・学習計画の策定、公布、実施は、こういったニーズに応えるものであると述べました。また、これまでに、公立・私立の教員、外国語センターの講師、そして学生たちが外国語教育・学習計画の目標達成に向けて大きな努力を重ね、成功に貢献してきたとも述べました。
トゥオン副大臣は、外国語教育・学習は内在的な必要性であると同時に、社会的なニーズや発展の潮流として極めて重要な役割を果たしていると強調したうえで、これほどまでに教育全般、特に外国語教育に有利な条件が整う一方で、多くの課題にも直面している時代はかつてなかったと述べました。
さらに副大臣は、人口規模や地域の多様性を踏まえ、まずは外国語学習の重要性に対する社会的な認識と理解を高めることが最優先課題であるとの考えを示しました。この認識に基づき国家外国語計画管理委員会が、得られた教訓の効果的な適用、外国語教育・学習計画の価値の発揮、さらには次のフェーズに向けたより実践的かつ効率的な実施ロードマップの策定に向けて提言を行うべきであると述べました。