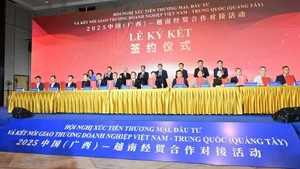この計画は、単なる戦略的枠組みにとどまらず、農業分野全体への行動喚起であり、気候変動への対応とグリーンで持続可能な農業の推進に向けたベトナムの国際社会に向けての決意表明でもあります。
作物分野の転換点
農業・環境省作物生産・植物保護局のフイン・タン・ダット局長は、同計画の発表会で、2035年までに作物分野の温室効果ガス排出量を2020年比で少なくとも15%削減することを目指すと述べました。これと並行して、主要農産物に対して「低排出」ブランドの開発と普及を進める方針です。
さらに2050年までには、主要な作物生産地域の100%で持続可能な栽培技術を導入することを目標に掲げています。ベトナムは、気候変動に責任を持つ農業発展の分野で地域の先駆けとなり、世界市場におけるグリーン競争力の確立と、COP26で表明した2050年ネットゼロ目標への貢献を目指しています。
気候変動の進行や、輸出先市場での環境基準の厳格化を背景に、農業の低排出化への転換はもはや不可避の流れとなっています。従来型の生産から、近代的で持続可能かつ責任ある農業への転換を進めることで、より高い経済価値を生み出すことができます。これが、「グリーン競争力」の土台となり、ベトナム産農産物が欧州連合(EU)や日本、北米など高付加価値市場へのアクセスを拡大する鍵となるのです。
この取り組みは、従来の栽培方法に比べて販売価格が10〜25%上昇するなどの直接的な経済効果をもたらすだけでなく、計画が効果的に実施されれば、年間800万〜1,100万トンの二酸化炭素換算排出量削減につながると見込まれています。これにより、国家の排出削減目標の達成と気候変動への適応力強化が大きく後押しされることになります。
2025年から2035年にかけて、作物部門は排出削減効果の高い主要作物に重点を置いて取り組みを進める方針です。
作物生産・植物保護局のグエン・ティ・トゥ・フオン副局長によりますと、同分野では34省・市で計59の具体的なモデルを導入することを提案しています。これには、低排出型のコメ栽培モデルのほか、コメと魚やエビの輪作、コメとトウモロコシや落花生の輪作などのシステム、さらにトウモロコシ、キャッサバ、野菜など特定作物向けのモデルが含まれます。また、茶、コーヒー、コショウ、カシューナッツ、かんきつ類、ドリアン、ロンガン、ライチといった永年作物向けのモデルも対象としています。
さらに、アグロフォレストリー(森林農業)モデル、循環型農業モデル、廃棄物再利用やバイオ炭生産モデル、さらには年間2期作のコメ栽培地を転換し、畑作物を導入するモデルなども含まれています。各省は、地域の実情に合わせて1〜3件のモデルを選定し、展開することが期待されています。
農業インフラの整備の必要性
ドンタップ省農業・環境局のレ・チ・ティエン副局長によると、同省は高品質かつ低排出型のコメ生産モデル21件を全国に先駆けて導入しており、これにより用水量を20〜30%削減し、生産コストを15%削減、メタン排出量も大幅に低減させる成果を上げています。
しかし一方で、低排出型生産の実施には依然として課題もあります。具体的には、投資資源の不足、企業に対する優遇策の欠如、グリーン融資制度の不備、そして作物ごとの詳細な技術指針の未整備などが挙げられています。
排出削減のためには、灌漑インフラの総合的な整備が必要だ。迅速かつ計画的に排水できなければ、先進的な栽培技術の導入は不可能である。したがって、灌漑への投資は転換を実現するための「不可欠の条件」だ。
カオ・ドゥック・ファット元農業農村開発大臣(現農業・環境省)
作物生産分野は、農業全体の温室効果ガス排出量の約8割を占めており、その主な要因は水田を常時湛水したまま栽培する方法によるメタン排出です。排出削減モデルを効果的に実施するためには、排水や水量の柔軟な調整が可能な灌漑システムの整備が欠かせません
元農業・農村開発大臣(現・農業・環境省)のカオ・ドゥック・ファット氏は、排出削減を進めるには、灌漑インフラを総合的に近代化する必要があり、水を迅速かつ計画的に排水できなければ、先進的な栽培技術を導入することはできないと強調しました。そして、灌漑への投資こそが低排出型農業への転換を可能にする「不可欠の条件」であると述べています。
さらに同氏は、各地方で計画を早期に実施できるよう支援するためには、作物生産・植物保護局が低排出型栽培に関する技術パッケージと研修資料を早急に整備・発行する必要があると付け加えました。
タイニン省農業・環境局のディン・ティ・フオン・カイン副局長は、「農業・環境省は作物構造転換の基準を早急に策定する必要がある」と述べました。効果的な実施を確保するため、同省は制度的枠組みを強化し、関連文書の見直し・改正・補足を進め、温室効果ガス削減要件を戦略、計画、プログラム、部門別計画に組み込む取り組みを進めています。
同省は同時に、低排出型作物栽培の基準や優遇政策、支援メカニズムの策定も進めています。現場での検査・監督を強化し、地域の課題に迅速に対応する方針です。さらに、技術指針文書、報告書の様式、排出削減結果の定期的なモニタリング・評価する手順も策定・発行される予定です。
ホアン・チュン農業・環境省副大臣によりますと、包括的なモニタリング・測定システムの構築は複雑な課題です。同省は傘下の研究機関に開発を委ねています。モニタリング・測定手順が確立され次第、農業分野でカーボンクレジット取引の試行を行い、段階的にカーボン市場への統合を進めます。同省はまた、気候変動局に対し、2028年までに国内でのカーボンクレジット取引を試行し、その成果を踏まえて国際的なカーボンクレジット市場への参入を目指すよう指示しています。