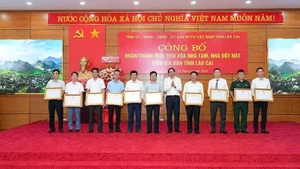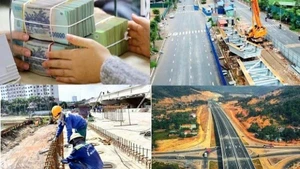禁煙オフィス
グリーン雇用の代表的な事例として挙げられるのが、コティア・サイゴン株式会社が手がける新規投資プロジェクト「ミサ・キャンパス・コンプレックス」です。同プロジェクトは、タン・トゥアン輸出加工区に位置し、総投資額は6,000億ドン(約2,280万米ドル)に上ります。ソフトウェア生産、ITサービス、技術移転コンサルティングといった、グリーン経済を支える主要分野に重点を置いています。
コティア・サイゴン株式会社のグエン・ティ・ゴアン取締役は、同社におけるグリーンジョブは、単に禁煙で低排出な職場環境をつくることにとどまらないと話します。それは、従業員がテクノロジーを使いこなし、人工知能(AI)を業務プロセスに取り入れることを求める、開放的で革新的な環境を育む取り組みでもあります。同社には約2,000人のスタッフが在籍しており、主に会計、教育管理、業務運営ソフトウェアの導入を専門としています。
また、タン・トゥアン輸出加工区では、従来型の産業モデルからグリーン化への転換を進める先駆的な地域として、テクノロジー企業の誘致や高度人材育成サービスの開発が進められています。将来的には、イノベーションセンターを設立し、市南部におけるスマート拠点の形成に貢献することを目指しています。
タン・タオ工業団地では現在、屋上太陽光発電事業を展開する企業が、設計エンジニア、設置技術者、システム運用コンサルタントの募集を行っています。同社の人事担当者によりますと、この分野は温室効果ガスの削減や生態系の保全、気候変動への適応に直接的に貢献しているといいます。
製造業に加え、クリーンエネルギーやグリーントランスポート分野でも新たな人材需要が生まれています。ホーチミン市内務局によりますと、再生可能エネルギーや電気自動車における労働需要は、2030年まで年間12〜15%の割合で増加すると見込まれています。これらの分野は、市が掲げる、2030年までに公共交通車両を100%電動化するという目標を実現し、2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロ(ネットゼロ)という国家目標の達成に貢献する重要な要素です。
国際労働機関(ILO)も、再生可能エネルギー、廃棄物管理・リサイクル、持続可能な建設、環境保護などの産業でグリーンジョブが急増していると報告しています。より多くの企業がクリーンな生産手法や環境配慮型技術を導入する中、「グリーン人材」への需要は今後も高まる見通しです。
成長を牽引するグリーンジョブ
人材紹介・採用コンサルティングを手がけるマンパワー・ベトナムのグエン・ティ・トゥ・チャン ブランドディレクターによりますと、グリーン転換によって2030年までに世界で約3,000万件の雇用が新たに創出され、労働市場の構造そのものが大きく変化すると見込まれています。グリーンジョブは、持続可能な素材工学や電気自動車の充電技術、スマート交通システムの運用、都市型農業の専門職など、あらゆる産業分野で広がりを見せています。
しかし、需要の高まりとともに人材の質に関する課題も顕在化しています。「雇用主の最大75%が熟練労働者の確保に苦労しており、94%の企業がESG(環境・社会・ガバナンス)基準を満たす人材の採用に困難を感じている」とチャン氏は指摘します。

グリーンジョブを真の発展の原動力とするためには、労働者自身がスキルアップや新たな能力の習得に主体的に取り組むとともに、企業や行政もこの転換を支える積極的な役割を果たす必要があります。雇用主は体系的な社内研修への投資を行い、教育機関はカリキュラムをグリーンかつ持続可能な発展目標に沿った内容へと整えることが求められています。
経済の中心地であるホーチミン市は、イノベーションとグリーン成長を軸とした新たな発展段階に突入しています。この文脈において、グリーンジョブは一過性の流行ではなく、市の持続可能な発展戦略の根幹を成す存在となっています。変革を遂げる工業団地、急成長するテック企業、クリーンエネルギー転換を促進する政策など、活気あるグリーン雇用エコシステムが着実に形成されています。
グリーン産業に即した包括的な人材育成システムの構築と、労働市場の需要予測が急務です。これには、国家機関、職業教育システム、企業が緊密に連携し、熟練した人材を育成するとともに、労働者にさらなる成長機会を提供していくことが重要となります。