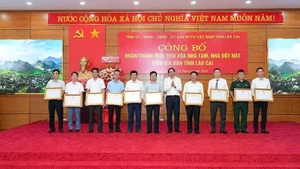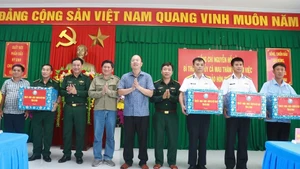1913年、スウェーデンは国民皆年金制度の導入を開始しました。当時、スウェーデンの人口の大半は農民であり、年金給付は主に工業労働者に限定されていました。そこで政府は、農民も年金を受け取れるようにすることで最低限の生活水準を保障するため、国民皆年金制度を導入しました。これにより、ほとんどのスウェーデン人が65歳で年金を受給できるようになりました。
1935年には、政策が変更され、富裕層を含むすべての国民が年金を受け取る権利を得ました。1948年までには、すべての人に同額の年金が支給されるようになりました。1999年には制度が改革され、年金額は最終15年間の収入ではなく生涯所得に基づいて計算されるようになり、退職年齢も柔軟に選べるようになりました。このモデルでは、長く働いた人ほど高い年金を受け取り、早期退職者は低い年金となるため、年金基金の不正利用を効果的に抑制する仕組みが整えられました。
スウェーデン政府はまた、定年年齢を引き上げましたが、特定の年齢は設定せず、最も早い退職年齢を61歳、最も遅い退職年齢を67歳と定めただけでした。統計によりますと、この改革後、早期退職をすると年金給付が減額されることを労働者が認識したため、平均退職年齢は大幅に上昇しました。全体として、スウェーデンの年金改革は、少子高齢化への対応と公平性の確保の両面で成功したと評価されています。国民皆年金制度のような大規模な政策は、慎重な計画と長期的なロードマップが不可欠であり、スウェーデンが現在のモデルを築くまでには60〜70年を要しました。
現在のベトナムでは、生産年齢人口のうち社会保険に加入していない人の割合が非常に高い状況です。ベトナム祖国戦線中央委員会傘下の研修・能力開発・科学研究院のグエン・カック・トアン所長によりますと、現在、社会保険に加入している労働者は約1,900万人で、全労働力の33%に相当します。その内訳は、行政機関や公的機関で雇用契約を結ぶ幹部職員・公務員・公的機関職員が280万人、企業で働く労働者が1,200万人、任意で社会保険に加入する自営業者が170万人、年金を受給している退職者が250万人です。一方、生産年齢人口の67%が依然として社会保険に加入していません。
より多くの人々に社会保険への任意加入を促すため、2025年の社会保険法では任意加入の仕組みが明確に定められています。国は、貧困世帯には月額保険料の50%、準貧困世帯には40%、その他のグループには20%を補助しています。しかし、任意加入者は依然として少なく、わずか170万人にとどまっています。
ベトナムでは急速な高齢化が進んでおり、2038年までに高齢化社会に突入すると予測されています。国会文化社会委員会のラム・ヴァン・ドアン副委員長は、年金制度改革を早急に進める必要があると指摘しています。ベトナムは多層的年金制度のもと、合理的なロードマップに従って徐々に定年年齢を引き上げています。国は労働参加の長期化を促進し、保険加入者を増やすとともに、健康で定年後もフルタイムやパートタイムで働きたい高齢者に対応した年金制度を整備することで、年金収入を増やし、社会資源の無駄を防ぐことが求められています。
現在、ベトナムでは年金を受給していない高齢者の貧困率が比較的高くなっています。経済成長や予算の余力に応じて高齢者への社会支援を段階的に拡大することが急務であり、同時に子どもへの投資も強化し、農村・都市・遠隔地間の栄養や教育格差の解消にも取り組む必要があります。こうしたバランスの取れた制度は世代間の連帯感と社会的合意の醸成にも寄与します。高齢化は社会保障制度をより包括的で持続可能なものへと改革する好機とも捉えるべきです。
2024年6月25日付の政令第76/2024/ND-CP号(弱者層向け社会扶助政策に関する政令第20/2021/ND-CP号の改正・補足)により、政府は基礎的な社会扶助基準を1人あたり月額36万ドンから50万ドンに引き上げました。この政策は、年金を受給していない80歳以上の高齢者、重度障害者、特に困難な状況にある子どもを持つ貧困世帯など、恵まれない人々の生活費を部分的に支援することを目的としています。しかし、この支援額は農村部の貧困ラインの33.33%、都市部の貧困ラインの25%にとどまり、支援の対象や水準は限られており、社会の一部の弱者層にしか及んでいません。
ベトナム婦人連合会のグエン・ティ・トゥ・ヒエン副会長は、国民皆年金制度の導入は、高齢者介護の負担を軽減し、生産年齢人口の労働市場への参加をより効果的に促進するとともに、社会全体の富の創出や経済発展にも寄与すると述べています。
一方、民族宗教省国際協力局のホアン・ティ・レー局長は、国民皆年金制度を成功裏に実施するには、十分な財源の確保が不可欠であると強調しました。財源は、労働者と雇用者の拠出で構築される社会保険基金を基盤とし、さらに所得税・法人税・付加価値税(VAT)や、正式に登録されていない小規模世帯事業への課税などによる国家予算で補うべきだと述べています。
国民皆年金制度への移行は、社会保障上の課題に効果的に対応するとともに、高齢期の労働者に安心の基盤を提供することになります。しかし、この政策を実現するためには、関係当局の強い意志のある取り組みと、労働者や社会全体の積極的な参加が求められます。